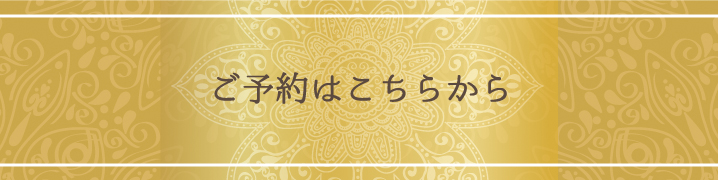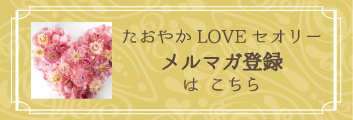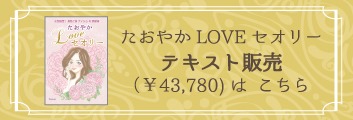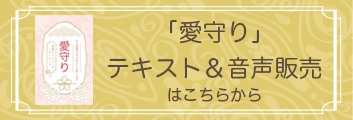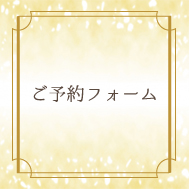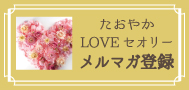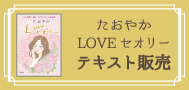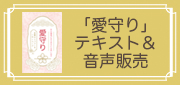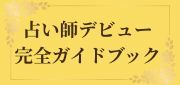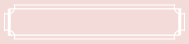- ホーム
- スピリチュアルコラム
スピリチュアルコラム
- トリニティ記事まとめ
- 新時代トリニティ&フラワーオブライフ関連の記事
-
効果的な「祈りの方法」 - どんな相談が多いの?
- 鑑定ってどんな感じ?
- 神社とお寺って何が違うの?
- お祓いって何をするの??
- 魂の栄養
- 神社参拝の手順
- 盛り塩の手順について
トリニティ記事まとめ
2030/04/13トリニティの記事をまとめています。
■祈りを忘れた人類は滅びる(スタンドFM)
https://stand.fm/episodes/6165db0331002e0006189620
■メンタリストDaiGoの炎上と災害(スタンドFM)
https://stand.fm/episodes/6118816e32f6ae0007e573dc
https://stand.fm/episodes/6118a195cbc5b60006afe184
■無条件の愛で戦うとは?
新時代トリニティ&フラワーオブライフ関連の記事
2028/06/01
その他のトリニティ、フラワーオブライフ関連の記事一覧はこちら
こちらのページにまとめています。
↓
フラワーオブライフ
https://rikopin.com/contents_702.html
アトラクションってなに?って話をまとめた記事はこちら
エゴを満たすことは悪いこと?この世界の仕組みを話すよ。
https://ameblo.jp/rikopinuranai/entry-12448816168.html?frm=theme
(YouTube)※音出ます。
【スピリチュアル】今、伝えたいこと
https://www.youtube.com/watch?v=NPoF4Jhw7Tk
人生変わるカモよ?
https://ameblo.jp/rikopinuranai/entry-12446282965.html
永遠の命を創りたい人は・・・
https://ameblo.jp/rikopinuranai/entry-12440911689.html?frm=theme
大ピラミッドの秘密、恐ろしい場所。
https://ameblo.jp/rikopinuranai/entry-12434351050.html?frm=theme
フラワーオブライフの真実
https://ameblo.jp/rikopinuranai/entry-12432632164.html?frm=theme
ピラミッドの秘密?
https://ameblo.jp/rikopinuranai/entry-12430969039.html?frm=theme
---------------
(ホームページブログ過去記事)
その他のトリニティ、フラワーオブライフ関連の記事一覧はこちら
https://www.rikopin.com/contentscate_214_29.html
https://www.rikopin.com/contents_541.html
ジャッジのお祭りだぁ!ワッショイ(笑)
https://www.rikopin.com/contents_540.html
輪廻転生の最終回を生きる私たち
https://www.rikopin.com/contents_539.html
今、伝えたいこと
https://www.rikopin.com/contents_538.html
あなたの魂は何色?色別診断。
https://www.rikopin.com/contents_537.html
あなたは台風に何を観たのか
https://www.rikopin.com/contents_536.html
永遠なんてない
https://www.rikopin.com/contents_535.html
聖なる/魔なる2ヶ月間
https://www.rikopin.com/contents_534.html
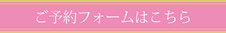
効果的な「祈りの方法」
2014/08/22
インテリジェンスフィールズさんのページから
転載させていただいております。
---------------------------------------------------
10年以上にわたり『祈り』の効果を客観的に研究している機関に
「スピンドリフト」という組織があります。
そこでは麦の発芽と『祈り』の関係を実験して、
祈り方や祈りの時間の長さ等々、
効果のある「祈りの方法」について調査をしました。
その結果、以下の7つの特徴がわかってきました。
1.『祈り』は実現する
麦の発芽の実験で、祈られたグループの種子のほうの
発芽率がはるかに高かった。
(何度実験しても同じであった)・・・・
『祈り』は発芽の成長に効果があった。
2.苦しい時ほど『祈り』の効果がある
発芽しにくいように、麦の種を浸している水に
塩分を加える実験で、塩分の濃度を増やすほど
(つまりストレスを多く与えるほど)
『祈り』の効果が大きかった。
このことから、祈ってもらう人が重い病気であるほど、
あるいは、つらい、不幸な境遇にあるときほど、
『祈り』の効果が大きいと思われる。
3.『祈り』の量は『祈り』の効果と比例する
麦の発芽の実験で、祈る時間を2倍にした場合は、
発芽率が2倍になった。
このことは病人のために祈る場合、時々、
祈る場合よりも、いつもその病人のことを思いながら、
できるだけ多く、『祈り』の念を送ってあげるほうが、
病人のためによいといえる。
4.対象を明確にした祈りが効果的
『祈り』が効果を持つためには、誰に対して祈るか、
或いは何に対して祈るかと、はっきり『祈り』の対象を
明確にして祈るほど、『祈り』の効果がある。
このことから、ただ漠然と祈るよりも、
「病気のAさん、Bさん、Cさん、Dさん」と
一人一人を意識しながら祈るほうが
効果が大きいといえる。
5.祈りの対象の数が増えても効果は減らない
種子を用いた実験では、種子の数が多くても少なくても、
結果は同じだった。
このことから、『祈り』の対象数がいくら増えて、
例えば1人の人への『祈り』であろうと、
5人、10人であろうとも、
『祈り』の効果は変わらないといえる。
6.祈りの経験の長い人ほど祈りの効果が大きい
実験によって、『祈り』の経験の長い人のほうが、
浅い人よりも大きな効果を生むということが分かった。
よって「困った時の神頼み」で、
急に思い立って祈る人よりも、
ふだんから神棚や仏壇に向かって
『祈り』をしている人の『祈り』のほうが、
効果が高いといえる。
その意味では、神主や僧侶、神父、牧師の
『祈り』の効果は大きいと思われる。
7.「無指示的な祈り」は、「指示的な祈り」より効果が大きい
「指示的な祈り」とは、例えば、ガンが治癒すること、
苦痛が消えることなど、
祈る人が特定の目標やイメージを心に抱いて祈ること。
いわば祈る人は宇宙に
「こうしてくれ」と注文をつける祈り方である。
無指示的な祈りは、なんらの結果も想像したり、
注文したりせずに、ただ、
「最良の結果になってください」とか
「神の御心のままにしてください」と
宇宙を信じてお任せする祈り方。
実験結果では、「指示的な祈り」と「無指示的な祈り」の
どちらも効果は上がったが、
「無指示的な祈り」のほうが
「指示的な祈り」の2倍以上の効果をもたらす
ことも多かった。
-------------------------------------------------------
文面は以上ですが、私が伝えたいことが1つと、
補足も1つさせていただきますね。
6.祈りの経験の長い人ほど祈りの効果が大きい
のところをお読みいただけましたでしょうか?
これは、本当にそうなんですよ。
ここに書いているようになるのがわかっているから、
神道のことや、守護霊の祈りをお伝えしているっていうのがあります。
客観的に見ていて、神棚に毎日祈ってる人と、そうでない人では、
思いを実現させたり、ラッキーが舞い込む機会が
明らかに違うというのを、日頃から感じていました。
神棚や祈りの習慣のある人は、そうでない人より「運が良い」んです。
私は、もう何年も毎朝神棚にご挨拶と感謝と祈りをしているのですが、
毎年毎年、祈りが届きやすくなりますし、
また、思ったことが引き寄せられるまでの時間が
毎年早くなるのを感じています。
もちろん、神様守護霊様が守ってくださってのこと、も大いにあろうかと思いますが、
実験した理屈で解明してもらえると、なお、確信が持てるというものです。
私は、これを皆さんにも実感してもらいたくて、
こうして日々、神様のこと、守護霊のこと、スピリチュアルなことを、
ブログや神楽祝会(かみたのかい)でお伝えさせて頂いています。
あまりいうと、宗教みたいになるので強くは言いませんが、
うちに来られてる方は、みなさん、
守護霊の祈りをお伝えして実践されていますね。
習慣になっている人は実感してもらえているようですが、
もし、やってるけど実感できない場合は、遠慮なく聞いてくださいね。
それと
7.「無指示的な祈り」は、「指示的な祈り」より効果が大きい
についても、補足をさせていただきますね。
鑑定に来られた方には、守護霊の祈りを伝えておりますが、
そのとき、希望やのぞみを具体的に祈ってくださいとお伝えしています。
それは、ここで書いている指示的な祈りになるかと思いますが、
ここに載せた実験の場合、祈りの対象がはっきりしていません。
うちでお伝えしている祈りは、祈りの対象が守護霊さんなので、
これとは対象が少し違ってくることをご了承くださいね。
守護霊の場合は、自分の担当(魂の教育係)なので、
具体的に祈ってから、気持ちの上では、
あとは、守護霊さん神様にお任せします・・・
という祈り方がベストになります。
ここが少し違っていたので、
祈りをやっている方が混乱してはいけないと思い、
補足させていただきました。
祈りの効果は想像以上のものがあります。
神棚のある方は神棚へ、
ない方も守護霊の祈りで十分効果がありますから、
やってみてくださいね。
まだお伝えしていない方は、
鑑定のとき聞いてくださっても良いですし、
会ったときでもかまいません。
遠慮なく聞いてくださいね。
どんな相談が多いの?
2014/07/27
占い初心者さんから聞かれる質問で
よくあるものは、
「どんな相談が多いんですか?」
です。
これについて回答していきたいと思います。
最近一番人気は、総合鑑定+リミットブレイク(R)です。
リミットブレイク(R)の詳細はこちら→★★★
50分のあいだにいろんな相談と、
心のブロックを解除できるリミットブレイク(R)を体験できるコースです。
短い時間で効果が高いため、おかげさまでクチコミで相談に来られます。
すぐに効果が出るため、より有意義な鑑定ができるので、とてもおすすめです。
リミットブレイク(R)は聞きなれない言葉なので、若干伝わりにくいのですが、
あのEXILEやドリカムも受けていますよ、と伝えると親しみを持って受け止めてくださります。
メンタルなブロックがない方は、総合鑑定50分13000円がおすすめです。
相談内容で多いものは、
女性の場合、やはり異性関係が多いです。
独身の方は、お付き合いしている彼とのこと、結婚についてや不倫など、恋愛や結婚の相談が多いです。
既婚の方の場合は、やはり夫のことや不倫について、お子さんのこと(進路や才能等)ですね。
女性で既婚独身関係なくあるのは、職場の人間関係ですね。
経営者の女性の場合、家族や異性関係のことについで、
経営の方向性や向き不向き(才能)についてが多いです。
全体的には女性にとって一番大切なのは、異性(彼、夫、結婚)のことのようです。
男性の相談では、経営者の方が多いので、経営相談、お仕事に関してが最も多いです。
やはり男性にとって仕事は、何をおいても大事なものなのだと思います。
仕事に関連して、新しいことをはじめる時期(吉日)なども多いです。
職場の人間関係(人事についてなど)もわりとあります。
次に夫婦問題の相談も多いですね。
その他、風水に関してや、引越しの日に良い日はいつかとか、
お祓いのご依頼も承っております。(場のお祓い)
鑑定料金等はこちらをご覧くださいませ→★★★
鑑定ってどんな感じ?
2014/07/10
占いをあまり受けたことがない方や、初心者の方にとっては、
占いでどのようなことをしているかわからなくて、なんとなく怖いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
最近は、占い初心者の方のご依頼も多くなりましたので、お申し込みから鑑定終了までの手順を記載してみますね。
1、お申し込み(ご予約メールかお電話にて)お申し込みをいただきます。
(すぐに自動メールが届きます。届かない方はご連絡くださいませ。)
2、幸粋より、日程の確定メールをさせて頂きます。このメールに鑑定所までの道順を送らせて頂いています。
(万が一スケジュールが埋まっている場合は、別の日程の提案をさせて頂きます)
3、当日になりましたら、お約束のお時間ちょうどにいらっしゃってくださいませ。
鑑定所では、相談者様が来られます前の10〜15分前に、場のお祓いをさせていただきまして、
祝詞を奏上し、鑑定でお力をお貸し頂く神々に許可を頂きます。
相談者様が来られます直前まで、相談者様の幸福と弥栄を祈りこみします。
(最良の状態で鑑定するために、これらの工程が必要です。
そのためにお時間ちょうどにいらっしゃって頂けるようお願いしております。)
※もしお早めに到着して時間を潰したい場合は、駅周辺の情報は以下のページです。参考にされてみてください。
深井駅のお店情報
http://rikopin.com/contents_127.html
4、約束のお時間に来て頂き、(お初めての方は)お申込書と簡単なアンケートをお願いしております。
5、お申込書の記載が終わりましたら、鑑定のスタートです。
鑑定の前に相談者様の守護霊様にご挨拶させて頂く祈りの時間を10秒ほど頂いてスタートです。
6、お初めての方は、まず生年月日から、その方の全体運や性格等を
先におおまかにお伝えさせて頂きます。
7、そのあとに本日の相談をお聞きして、鑑定していきます。
総合鑑定と総合鑑定+リミットブレイク(R)コースは、50分間の時間内でしたら、
ご本人にまつわることなら、何個相談くださってもかまいません。
(メニュー表はこちら→★★★)
今、迷っていること、心配なこと、困っていることを自由にお話くださいませ。
延長される場合は10分につき1000円の延長料金になります。
・鑑定の内容により、四柱推命、霊感、カード等、様々に使用します。
・鑑定結果とアドバイスは、覚書に箇条書してお渡ししております。
(内容を忘れてしまうこともあろうかと思いますので、念のためお渡しします)
・ご希望の方、もしくは必要と思われる方には、鑑定内に願いが叶う守護霊の祈りの手順をお伝えします。
必要な方はおっしゃってくださればお伝えしますので、おっしゃってくださいね。
8、天然石お守りブレスレットのご依頼がある場合は、鑑定終了時に伝えて頂ければ、
サイズをお測りします。(8000円〜30000円の間でご希望の額で作成します)
9、次回のご予約をされる方は、最後に次回のご予約をされて終了です。
10、最後に幸粋からの快運つうしん(手作りの新聞)と、イベントの最新情報などをご案内や
お渡ししてお見送りさせて頂きます。
ここまでが一連の流れですが、もしわからないこと等ございましたら、
ご予約フォームの「問い合わせ」を選択頂いて、お問い合わせいただくか、
お電話にておたずねくださいませ。
※完全予約制となっております。前日の15時以前にご予約をお願いします。
前日に翌日こられます方のことを神様にお伝えする必要がありますので、
申し訳ありませんが、当日のご予約はお受けしておりません。
ベストな状態で鑑定させていただけるよう、お早めのご予約のご協力をお願いいたします。
神社とお寺って何が違うの?
2014/07/04
神社とお寺、なんとなく似てるような似ていないような・・・・
その違いって何でしょうか?
案外わかっていない神社とお寺の違いについて、
初心者さんにわかるように、簡単に説明させていただきますね。
【祀っている対象の違い】
神社とお寺は祀っている対象がそれぞれ違います。
神社⇒八百万の神々、神様や自然を祀る(神道)
※人や動物など眷属(眷属(けんぞく)=神様のお使いである動物)と呼ばれる存在を祀っているところもあります。
お寺⇒仏様を祀る(仏教)
【お参りの仕方の違い】
神社⇒二礼二拍手一礼( 二拝二拍手一拝)で、日頃の感謝を伝えたり、お願い事をする。
※出雲大社(は二拝四拍手一拝)のように、作法が違う神社もあります。
お寺⇒胸の前で合掌して手を合わせるだけ(柏手は打たない)
【こんなときはどっちに行けばいい?】
神社⇒初詣、七五三、結婚式、厄除け
お寺⇒お葬式
※一部、神社でお葬式される方もいますし、お寺で結婚式をあげられる方もいらっしゃいます。
【宗教なの?】
神社⇒宗教ではなく思想なので教えはない。
※神道は古(いにしえ)から伝わる、自然崇拝の思想です。
ちなみにお正月やお祭りも神道の習わしです。
お寺⇒宗教で教えがある。インドのお釈迦様が開祖です。
【お寺と神社が同じ場所にあるのを見たことがある?】
神仏習合という考え方
日本には古(いにしえ)から自然崇拝の思想である、神道(しんとう)が元々ありましたが、
その後、仏教が日本に伝わってきました。
日本には、外来宗教である仏教を拒絶することなく受け入れる流れがあり、
神道と仏教を融合させる考え方が伝わるようになりました。
そういった経緯があることから、神社とお寺が一緒にある場所もあります。
お祓いって何をするの??
2014/07/02
【古神道音霊(おとたま)祓いとは?】
幸粋開運鑑定事務所のメニューには、古神道音霊(おとたま)祓いというお祓いがあります。
このお祓い、祝詞(のりと)や古い言葉を奏上するため、
何をやっているかわかりにくいところがあろうかと思います。
お祓いで行っている内容を、なるべく簡単に誰にでもわかる言葉で、
解説していきたいと思います。
巫女鈴を使った音霊(おとたま)祓いは・・・・・・
まず、場と自分に対して心構えや気持ちをととのえる祝詞(のりと)を奏上します。
そのあとに、神様をお招きする準備の祓えをしていきます。
禊祓(みそぎはらい)いと大祓(おおはら)えです。
禊祓いは簡単なお掃除で、
大祓えは大掃除みたいなものと思ってもらえれば、わかりやすいと思います。
つまり祓えとは、言葉(言霊・ことだま)によって、「場」を浄化(大掃除)するんです。
理由は、神様をお招きするにあたり、場が清浄でないといけないからです。
大掃除のあとも、秘伝のものをいくつか使って、何度も何度も場を細かく掃除します。
とにかく清く清く、神様をお招きする前には、何度も清めていくんです。
それでようやく清まったという頃に、
神様に降りていただくための、密呪をあげさせていただき、
ようやく神様に来ていただきます。
このとき来ていただく神様は、だいたいは地元の産土様(うぶすなさま)です。
神様に来ていただいたら、次に神様を讃(たた)える祝詞(のりと)を奏上します。
わかりやすくいうと、素晴らしい神様がいらっしゃって尊いです。とてもありがたいです。
というような感じの内容の歌を唱えるんです。
こうしてまず、来ていただいた神様に喜んでいただくんですね。
人間でも
「ようこそいらっしゃいました。あなたを心待ちにしていました。
来てくれてすごく嬉しいです。大変ありがたいです。感激しました!!」
と訪問した開口一番言われたら?
悪い気はしませんよね。
神様も同じなんですよね。
お招きして来てくださった神様を、祝詞(のりと)で丁寧に讃(たた)えていきます。
そうして、神様が良い気持ちになられた頃に、
神様の祓(はら)えのお力をお借りしながら、巫女鈴を使って場を祓っていきます。
東西南北を順に鈴(の音霊)を使って、鈴を鳴らしながらお祓いをします。
そのときも、密呪を唱えて祓います。
それが終わったら、
神様に帰っていただくための祝詞を奏上して、神様に帰っていただきます。
と、これでだいたい完了です。
神社でも巫女さんが舞を舞っておられますが、
あの舞も、神様に喜んでいただくための舞です。
お願い事をする前に、まず神様に喜んでいただき、
それからお願い事をお伝えします。
喜んで頂いてから、お願いしたり、お力を貸していただくと、
神様も喜んで人のために祓いや願い事を叶えるようにと、進めてくださると思います。
魂の栄養
2011/10/17
人は生きるために食べ物から栄養を取り入れ生きています。
それと同じで、本来は魂にも栄養が必要なんですね。
生きていると、いろんなことがあります。
嫌な思いをしたり、辛い思いをしたり、悲しい気持ちになったり。
すると、気が枯れてくるんですね。気が枯れるのを、気枯れ(けがれ)といって、気枯れは穢れです。
体が疲れたらゆっくり休んで、栄養を取り入れれば元気になりますが、気枯れはそれだけだと治りません。
気枯れは、魂の栄養不足で、魂がやせ細った状態をいいます。
気が枯れるとどうなるかというと、以下の感情が出てきます。
寂しい、虚しい、悲しい、泣きたくなる、あきらめ、やる気が起きない、刹那的、厭世感にさいなまれる・・・
※厭世感(えんせいかん)・・・世の中をいやなもの、人生を価値のないものと思うこと。
いま、日本には魂がやせて気が枯れた人が多いみたいですが、
上記の感情になるのは、気が枯れている症状です。
では、枯れた気を甦らせ、イキイキした魂になるにはどうすればよいでしょうか?
答えは、・・・・・・神様に会いにいくことです。
神様に会いにいくと、魂に栄養をたくさん頂けるので魂が肥えてきます。
神社にいくとスッとするのは、神様から魂の栄養を頂いたからなんですね。
ですから少々のもやもやなら、神社参拝で吹き飛びます。
日本人は、古来よりずっとそうやって神様や自然を信頼して生きてきた民族です。
今、日本に元気がない理由のひとつは、神様の存在を忘れてしまっていることに由来すると、私は感じています。
日本の神様は自然が神様ですから、神道は宗教ではありません。
人間も自然の一部ととらえ、敬意を持って接してきたならわし、幸せになる方法のひとつです。
人は魂と肉体両方が整って、バランス良く健やかに生きていけるのだと思います。
実際に、鑑定をしていても、神様に参らない方は、気が枯れている方が多くいらっしゃいますし、
参っていないのを参るようになったら、元気になられるんですね。
ですから、気が枯れたときは、神社にいって神様に素直な気持ちを伝えて、魂の栄養をいただくといいと思います。
神様といっても、大きい親(自分の親よりも、もっと大きい愛の存在というイメージ)
に甘えるような気持ちで、素直に話しかけていいんですよ。
その素直な気持ちが神様と繋がりやすくなるコツです。
折に触れ、神様お元気ですか?いつもお守り頂きありがとうございます。
私はいまこれこれこうで、これから○○を頑張りますので、宜しくお願いしますといつも意識して、
自分から神様に近づいていくことが大事です。気が枯れたら、ぜひやってみてください。
神社参拝の手順
2011/10/03
【神社参拝の手順について】
まず神社の敷地内に入るときに、鳥居を通ります。
この時に軽く鳥居にお辞儀します。
その後、てみずや(手を洗うための水があるところ)に行き、手を清めます。
- ひしゃくに水を汲んで右手で持ち、左手を清めます。
- 今度は左手で持ち、右手を清めます。
- 再度右手にひしゃくを持ちかえて、ひしゃくの中にある水を左手のひらに移し口を清めます。
(水は飲まない。うがいもしない) - (左手に口が付いたので)左手をもう一度清めます。
- ひしゃくの持ち手を清めます。
(ひしゃくをまっすぐに立てて水をひしゃくの持ち手にかけます。)
※これらの作法は、手を洗うという概念ではなく、「清める」ということになります。
(ですから、ここでうがいをしたり、ひしゃくに口を直接つけてゴクゴク水を飲むのは違いますよ。)
手を清めたら静かに歩いて(ベラベラ無駄なおしゃべりはなるべくしないほうが良いです。)
神殿の前まで行きます。
神様に一礼してから、お賽銭をそっと入れます。(遠くからポーンと投げないこと。)
その後、鈴があれば鳴らします。
2礼、2拍手、1礼をしてから、神様へご挨拶と祈りをおこないます。
その他、祈りが届きやすくなる方法など、詳細はブログに記載していますので、
参考にされてみてください。
盛り塩の手順について
2009/09/18家の中の「気」を清浄にして清めるためには、盛り塩が最適です。
玄関やトイレ、家の四方に盛り塩を置いておくと、邪の「気」から家を守り、開運につながります。
盛り塩の手順について、今回のコラムでは基本的な方法を記載しますね。
盛り塩をどう設置していいかわからない方もいらっしゃる方は参考にされてみてください。
※盛り塩はいろいろな方法がありますが、一般的な方法を記載しています。
この方法でなければいけないということではありません。
盛り塩をしておくと良い場合
- 家や事務所などで、いろいろな人を招いて仕事をしている方。
- 占いやセラピーなど、人の「陰」と関わる職業の方。
- 不特定多数の方を相手にお商売をされている方。
- 家の中で何か不穏な感じ(気味が悪い感じや不安な感じ)がする場合。
- 新しい家に引っ越したとき。
- 霊的に敏感な方。
- 不吉なことが立て続けに起きた時。
- 開運したいとき。
・・・など。
盛り塩に用意するもの
-
- 盛り塩用の塩(自然塩です)
- 小皿 半紙(お皿の大きさにカットしておく)
- 木型(もしくは、厚紙で三角形を作成する)
- へらなど
-
木型や盛り塩用の塩、へらなどは、ネットショップなどの神具ショップ等で販売しています。
検索で「盛り塩」とか「盛り塩固め器」と言うキーワードであがってくると思います。
お皿や半紙は、100円均一などにおいているもので十分です。
-
塩がさらさらしている場合は、用紙などをしいた上に塩を置いて、霧吹きなどで少し湿らせてから使いましょう。
(あまりにもさらさらした塩だと、型がつきません。)
-
木型に塩を半分程度入れたら、一度手でぎゅっと押さえて、塩をしっかりと入れていきます。
(このとき入れ方がゆるいと、形がきれいになりません)
-
小皿にカットした半紙をしいて、その上に木型を置き、逆さにして中身の塩を出します。
盛り塩の設置場所は、玄関やトイレ、部屋の四隅です。
全部おいてもかまいませんし、気になる場所だけおいてもかまいません。
どこかひとつ置きたい場合は玄関がよいです。
取替え時は、できればまめに取り替えるのが良いですが、1週間〜2週間程度おきに取り替えるとよいでしょう。
トイレに置く場合は、四隅に置いて部屋よりも、よりこまめに取り替えるようにしましょう。
もし木型がない場合は、厚紙などで三角錐を作って代用してもかまいません(8センチ角程度の三角錐が最適です)木型は円錐のものでもかまいません。