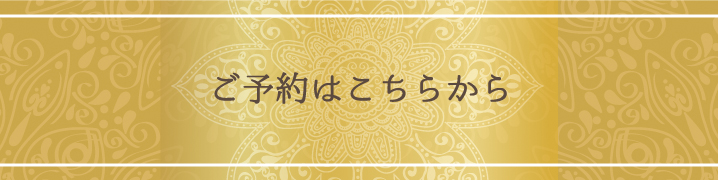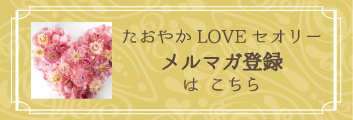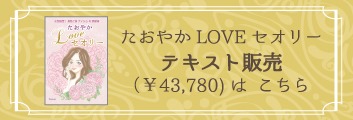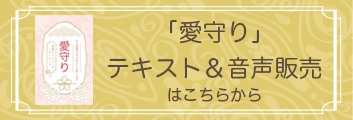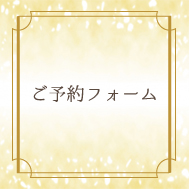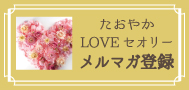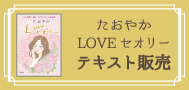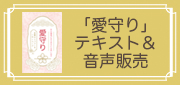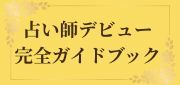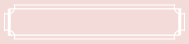- ホーム
- スピリチュアルコラム
スピリチュアルコラム
スピリチュアルなお話
2008/10/04占いとは関係ありませんが、この世の法則をうまく表してるお話しです。
「天国と地獄のお話」 ・・・・・
ある男の人が生死の境を彷徨って、無事生き返った時にされた話だそうです。
その男は、とても好奇心が強かったので、あの世の番人に「是非、天国と地獄がどんな所か見せて欲しい」とお願いしました。
すると、その番人は快く2つの部屋を案内してくれました。
一方の部屋には“天国”の看板が、もう一方の部屋には“地獄”の看板が。
扉を開けると、どちらの部屋も、ちょうど食事が始まる時間でした。
でも何故か、どちらの部屋も、全く同じ様子、光景だったのです。
大きなテーブルには、沢山のお皿が並び、いずれのお皿にも、とても美味しそうな食事の数々が盛られているのです。
テーブルの周りには、何万という椅子に座る人の列が。。。
その男は不思議に思い、番人に「素晴らしい環境で、どちらも全く一緒ですね。これは両方天国じゃないのですか?」と尋ねたところ、番人は「これが天国と地獄ですよ。よく見てごらんなさい」と返事しました。
なるほど、男がもう一度よく見てみると、どうも様子が違う。
どちらの部屋にいる人達も、皆、左手を椅子に縛り付けられて、右手には何故か1メートル以上もの長さのある箸が縛り付けられている。
ここまでは、どちらの部屋も同じだ。
でも、天国にいる人達は、皆健康そうで顔色も良く、ニコニコとし、部屋全体が幸せそうな空気に包まれているのに対して、地獄にいる人達は痩せこけ、骨と皮ばかりになっていて顔色も悪く、おまけに殺気立った表情をして、部屋全体が殺伐とした空気に包まれている。
一体、何が違うのか???
しばらくすると、どちらの部屋にも食事開始の合図が鳴り響き、皆が一斉に食事を始めます。
すると。。。
地獄の部屋では、一人一人が必死になって、長い長い箸で料理をつまみ、自分の口に持っていこうとします。
でも勿論、1メートル以上もある長い箸ですから、自分の口に上手く料理を運べるわけがない。
必死になって同じ行動を繰り返しても、美味しそうな料理は次から次へとテーブルや床の上にこぼれ続けます。
そして暫くすると、何故か各々が争いを始めます。
どんなに必死になっても一口も料理を食べられないストレスに加えて、ひょっとすると、自分の目の前にある料理を誰かに取られるのではないか。。。
各々が、必死に長い箸を使って、周りの人を傷つけて妨害しようとします。
それはそれは、あまりにも悲惨でおぞましい光景でした。
そこで男は、隣の天国の部屋に目を移しました。
こちらでは、一人一人がお互いに声を掛け合いながら、長い長い箸でつまんだ美味しそうな料理を、隣の人に食べさせてあげているのです。
お互いがお互いに食べさせてあげているので、食べられない人など一人もいなくて、お互いに、「どうぞ」「ありがとう」と声を交わしながらニコニコと。。。
時が経ち、再び食事終了を告げる合図が鳴り響き。。。
天国の部屋の人々は皆満足して、部屋全体に幸せな空気が。
地獄の部屋の人々は、結局誰も一口の食事をとる事も出来ず、より一層殺伐とした空気が。
男は番人に答えました。
「これが“天国と地獄”の正体だったんですね。よく分かりました、ありがとうございます。」
命術・卜術・相術について
2008/10/04<占い一般知識>
占いには、大きく分けて、命術(めいじゅつ)、卜術(ぼくじゅつ)、相術(そうじゅつ) の三種類のジャンルがあります。
命術は生年月日を用いて、個人の性格や一生の運勢や他人との相性などを占う術です。
卜術とは、偶然に表れた象徴を用いて、事柄や事態の成り行きを占います。
相術とは、対象を外側から見ることによって、その人の状態や運勢などを占います。
それぞれの主な占術については以下です。
「命術(めいじゅつ) の種類」
四柱推命(しちゅうすいめい)
中国の代表的な命術のひとつです。
年・月・日・時の各干支(えと)八字を並べて四つの柱として「命式」を作り、その命式から個人の運命の吉凶、禍福(かふく)、成敗、貴賤、貧富など一生の運命(命)を推し量ります。
生まれた時間の十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)、十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)という一見シンプルな素材を使いながらも、その判断は大変複雑といわれる玄人好みの占術です。
西洋占星術(せいようせんせいじゅつ)
「星占い」でもおなじみの12星座を使った西洋の代表的な命術です。
生年月日時の惑星位置と出生地の緯度・経度を基にホロスコープという図表を作成し、個人の個性・性格や価値観および一生の運命などを分析します。
また、個人が生まれてから死ぬまでの間にどのような変化や成長をするのか、どのような出来事にいつ遭遇するのかといった変動していく運命を予測することもできます。
紫微斗数(しびとすう)
四柱推命と双璧をなす中国の代表的な命術で、生年月日時を基に個人の性格から一生の運命までを読み取ろうとする中国版占星術です。
紫微(しび)とは北極星の別名で、この紫微星を中心に他の多くの星々を使い、個人の運命(数)をはかる(斗る)ことから紫微斗数と呼ばれています。
仕組みの分かりやすさと的中率の高さを兼ね備えているため、台湾では現在最もポピュラーな占いとして一般に広く普及しています。
「卜術(ぼくじゅつ)の種類」
断易(だんえき)
周易でも用いる「六十四卦(ろくじゅうよんか)」と、占う年月日を組み合わせて占断する卜術です。
サイコロ、コイン、筮竹などを用いて「六十四卦」を立て、各卦を構成する六つの爻(こう)に定まった十二支を割り振り、これらの十二支と占いを立てた時の十二支の陰陽五行による関係を基に判断するため、別名「五行易(ごぎょうえき)」とも呼ばれています。
占いたい事柄に対する吉・凶がはっきり出る上に、その結果の出る時期と当事者にとって有利な対処策まで答えられる占術です。
タロット・カード
恋愛、人間関係、ビジネス、その他人事全般について占う西洋の代表的な卜術のひとつです。
ルネサンス期前後より西欧世界に伝わるタロット・カードという道具を使い、質問内容に対して偶然にレイアウトされたカードの絵柄やシンボルから、イメージを広げていく占いです。
周易(しゅうえき)
テレビドラマなどに出てくる占い師といえば、よく細い竹の束を使っています。
あの筮竹(ぜいちく)やサイコロ、コインなどを用いて八卦(はっけ、はっか)と呼ばれる基本シンボルを組み合わせ、「易経(えききょう)」という中国の古典に照らし合わせて解釈していきます。
だれでも簡単に習得できる分かりやすさと、内容的には底知れぬ奥深さを兼ね備えた占いです。
また、易の思想は全ての中国占術の根底に流れる根本思想でもあり、さらに人生哲学としても大いに活用できる内容を秘めています。
梅花心易(ばいかしんえき)
中国の北宋時代(11世紀)に完成されたといわれる易占法です。
周易で用いる八卦(はっけ、はっか)や六十四卦(ろくじゅうよんか)の体系を基本としますが、判断の基となる易卦(えきか)を出す際にあえて道具を使わず、占断する年月日時や周囲のあらゆる物から数を取って易卦(えきか)を立てるというのが特徴です。
また、断易のように占う事柄の吉凶を判断できるメカニズムも備えているため、周易と断易のそれぞれの長所を併せ持つ易占法であるとも言えます。
「相術(そうじゅつ) の種類」
手相(てそう)
手や爪の形やその色つや、および手のひらに記されたさまざまな線や紋様の状態から、その手の持ち主の個性・体質・健康状態・生活状態、さらに来たるべき運命などを占う方法です。
人相(にんそう)
頭部や顔の形、目鼻などの各パーツの形や付き具合、顔面の色つやあるいは表情や動作・立ち居振る舞いなどを総合して、その人の個性や体質・健康状態および生活状態や来たるべき運命などを占う方法です。